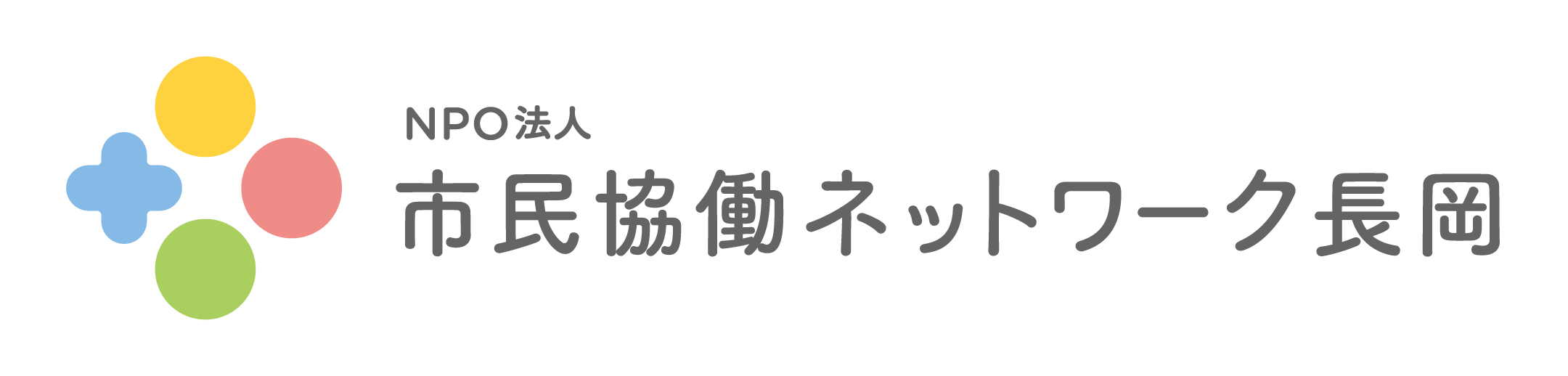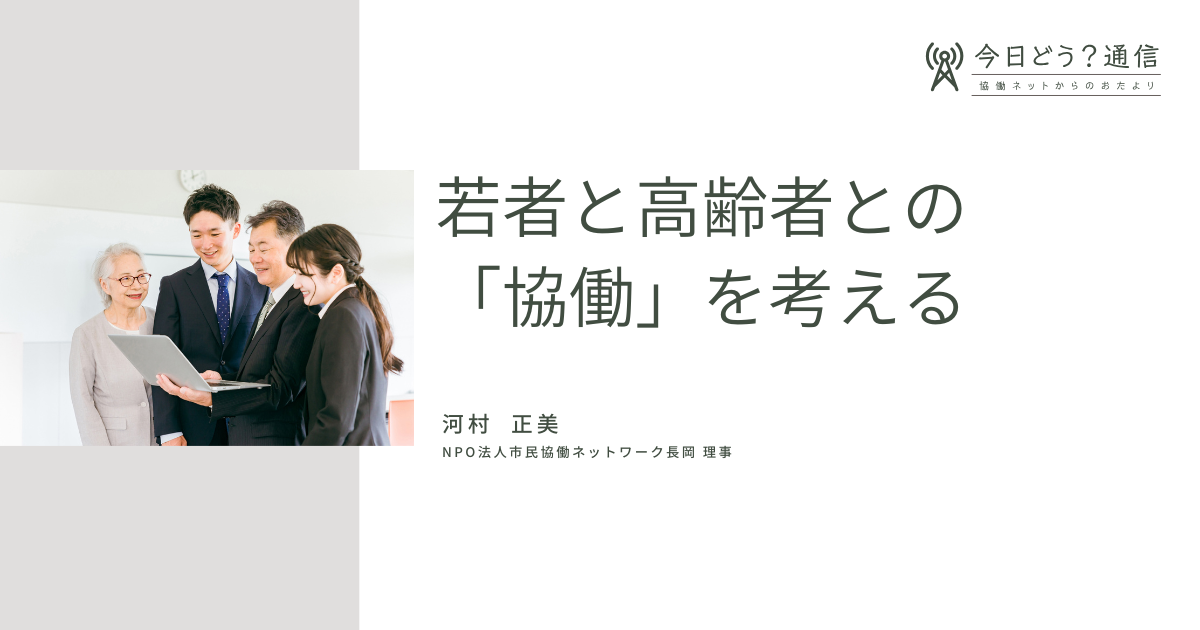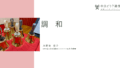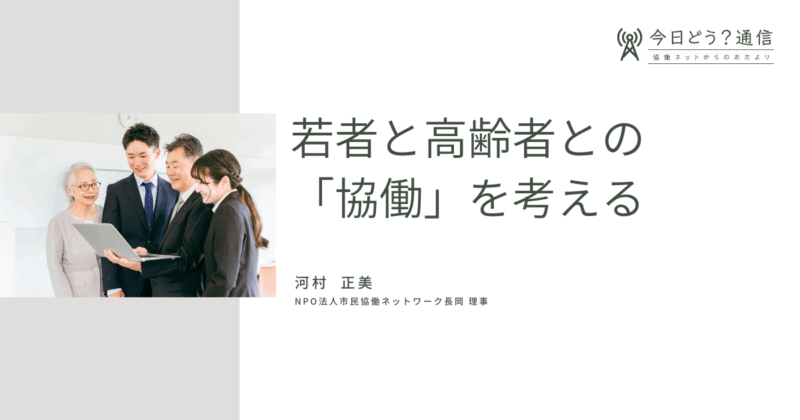
「協働」という言葉に出会って20年近くが経ちました。
この間、一番学んだことは「違いを生かす」ということです。それぞれの立場、違う経験、違う感性、違う能力…、そうした違いを認め合い、補い合うことで新しい価値を一緒に実現していく――。「多様性」「共感」「集合知」がキーワードです。
気がつくと、私も70歳を超えてしまいました。今回、この原稿依頼があり、「協働」について思いを巡らすと、「若者」と「高齢者」(年寄り、老人、年配者、熟年者、シニアなどいろいろな言い方がありますが)との協働ということが頭に浮かんできました。
年齢を重ねていくと、少しずつ体力・気力が衰えていきます。それでも、これまでの経験や知識など、若い人たちに伝えることはいろいろあると思っていました。しかし、いざそうした年齢になってみると、その予想はいささか違っていました。若い人に教えることより、若い人から教えてもらうことの方がはるかに多いというのが実感です。
例えば、デジタル社会の進展に伴う情報格差の問題です。デジタル庁の重点計画でも、高齢者は「デジタル社会の恩恵から誰一人取り残さない」対象として意識される存在になってしまっているのです。
~目は霞み 耳に蝉鳴く 葉(歯)は落ちて 霜(白髪)を頂く 歳の暮れかな~
これは、老いていく姿を四季に読み込んだ禅僧の歌と言われます。「老い」とともに、こうした身体的な変化が押し寄せてくる中で、これまでの人生経験が通用せず、新たな対応を余儀なくされることが山のようにあるのです。
また一方で、若い人たちも、絶えず新しいものを追いかけながらも、自分がどんな価値観をもち、何を学び、どんな能力を身に着けていけばよいのか、不安を抱えながら懸命に生きているようにも見えます。
そんな状況の中で、若者と高齢者との「協働」ということですが……
まず若い人たちに期待されるのは、さまざまな活動にデジタル化などの恩恵をどんどん取り入れていくことにチャレンジしていき、新たな成果や可能性を地域社会に示していくということです。そしてできれば、その成果が子どもから年配の人たちにも行き渡るようにサポートすることまで目を向けてほしいということです。
これは端的に言うと、若い人たちのデジタル技術や知識を高齢者などが主体の活動にも力を貸してほしいということでもあるのですが、一方的な支援活動ということでもありません。世代間交流は、それぞれの自己効力感や達成感を高めていくとともに、交流や会話などを通して多様性の理解を深め、しなやかな想像力を育て、コミュニケーション能力の向上を促すなど、さまざまな効用が活動報告や研究レポートなどで示されています。
一方で高齢者に期待されるのは、やはり長い人生の中で蓄積してきた知識や経験の披露と伝授です。
急激な変化への対応に追われる中で、自分の体験や考えに自信をもてない、若い人に余計なことは言わないという高齢者も増えています。しかし、それがいま役立つか否かは受け取る側で判断すればよいと割り切るくらいでいいのかも知れません。周りの人と共感をもって取り組むことができた経験を若い人たちと共有し、そこに新しい伝達ツールを活用した工夫などが加わることで、今までになかった価値が生まれることも夢ではありません。
また、私の周りの同年代の人たちがよく口にする言葉があります。「まあ、だいたいそんげんもんらて」「そうそううまくはいかんて」「またやってみればいいこって」……
ちょっとおどけた調子で発せられることも多いこの言葉、単に慰めとも違います。長い人生経験からそう簡単にはいかないことを知っているのです。特に若い人に向かっては、新たなことにチャレンジしたその行動力をたたえ(うらやましがり?)、めげずにまた挑んでほしいという純粋な気持からなのです。心のいいクッションにもなると思います。
違うからこそ一緒にやる価値がある――「協働」の核心です。そういう意味では、年齢という人生の重要な構成要素の違いをもつ「若者」と「高齢者」が協働するのは、いいことがありそうです。
文・NPO法人市民協働ネットワーク長岡 理事 河村 正美
◆―――――――――― ◆
「今日どう?通信」はNPO法人市民協働ネットワーク長岡の事務局・理事その他関係者が、市民協働をテーマに日ごろ感じたこと、気づいたことをしたためるリレーエッセイ・コラムです。
感想など、お気軽にコメントなどでお寄せ下さい。