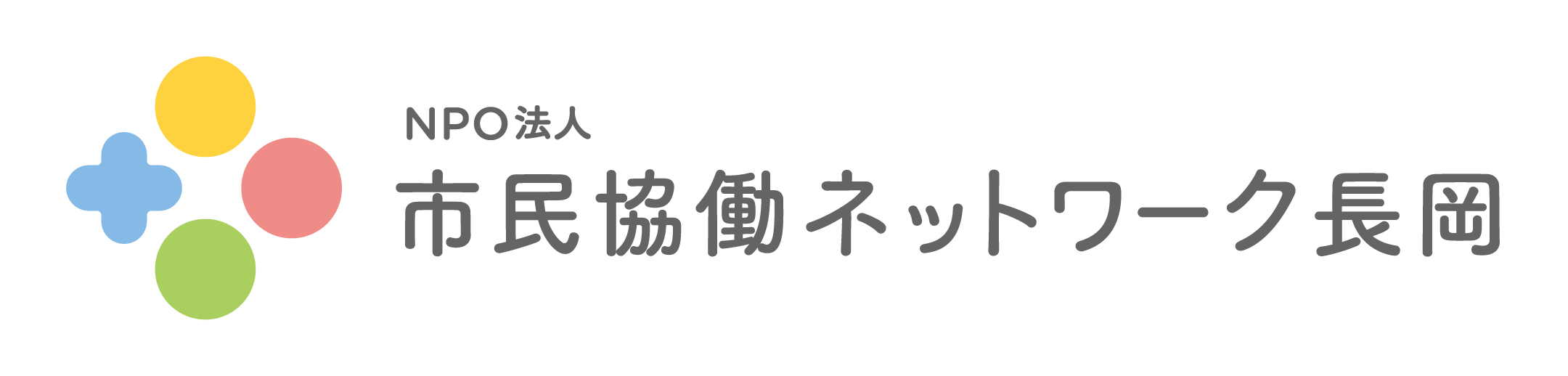第二次審査 投票フォーム【夢の種プロジェクト2024】
あなたが最も共感できて、推したいと思うアイデアはどれですか?
全5件のノミネート作品をお読みいただき、ページ下部の回答フォームにてお答えください。
お花で幸せを紡ぎだす、花いっぱいの町プロジェクト
山本 千佳子さん
ニーズ・背景
若い世代が地域社会や伝統文化に触れ合う機会が少なくなっていると同時に、学生たちの自己表現や主体性を育む場も限られてきている。長岡市内のある高校の華道部は部員が減少し、廃部の危機に直面している。その背景には、華道の魅力を伝える機会の少なさや、華道が「難しそう」「敷居が高い」というイメージがあると考えられる。加えて、日本の伝統文化の認知が薄まりつつあり、また規格外で廃棄される花が増えている現状も問題となっている。これらの課題を解決し、地域全体で「花」を通じた活気づけを行うために生まれたアイデア。
動機
家庭教師の仕事をしている中で、生徒から「華道部が廃部の危機にある」と相談されたことがきっかけ。その生徒の熱意や悩みを聞き、華道の魅力をもっと多くの人に伝える必要性を強く感じた。生け花を地域に発信することで生徒たちが主体的に行動し、自信を持てる経験を提供したい。それによって華道部が面白そうなことをしている、と認知させたい。またSDGs活動として廃棄される花を有効活用する仕組みを作ることで、社会的意義を持つ取り組みにしたいと考えた。
過去にキッチンカーを使った販売体験を生徒たちと行った際、生徒たちが「自分たちで考え、行動し、成果を出す経験」を通じて自分の得意分野と将来を真剣に考えるきっかけになったこともあり、華道を活用した取り組みであれば、伝統文化の継承に加え、生徒たちの主体性や地域とのつながりを深める活動として発展させられると考えたから。
実施内容
対象者
長岡市内の高校生(特に華道部や地域活動に興味を持つ生徒)
長岡市内の企業・店舗の協力者
花の生産者や花屋、地域住民
期間
企画開始後、約半年を準備期間とし、その後継続的に実施。
内容
生徒たちがマーケティングリサーチ、営業活動、会計管理、企画立案、生け花制作といった幅広い活動を実際に行う。規格外で市場に出せない花を提供してもらい、生徒たちがそれを活用し生け花を制作することで、廃棄される花を有効活用する。
また、長岡市内の企業や店舗、個人宅に生徒たちが制作した生け花を飾らせてもらい、その際に協賛費用や提供費用をいただく。活動を通じて得た余剰金を活用し、生徒たちの作品展やワークショップを開催するほか、地域住民との交流イベントを実施する。
場所
長岡市内の企業や店舗、学校、地域の公共スペース
協力者
長岡市内の学校、華道部生徒、花屋、生産者、地域ボランティア
期待する効果
教育的価値
生徒たちが経済活動を含む実践的な学びを体験し、将来への自己表現力や主体性を育む。
伝統文化の継承
生け花を通じて日本の伝統文化を次世代に伝え、地域に根付かせるきっかけを作る。
SDGsへの取り組み
廃棄される花を有効活用し、環境負荷軽減を目指す。
実現に向けて足りないもの
資金援助
花や花器、運搬費用、活動広報費用のための資金が必要。
協賛企業・店舗の募集
生け花を飾らせてくれる企業や店舗を増やしたい。
お花や資材の提供者、連携体制
規格外の花を提供していただける生産者や花屋の協力が必要。
他の学校の華道部や地域活動を行う団体とも連携し、取り組みを広げるためのネットワーク作りが必要。
地域ボランティアの参加
生け花指導や運搬作業をサポートしてくれる方々が必要。
おじいちゃんおばあちゃんと遊びましょ
永井 優子さん
団体名
NPO法人ミュージックライフパートナー
団体の目的または設立の背景
一般市民(特に学生や高齢者、障がいを持つ方)に対して、コンサート活動に関する事業を行い、音楽を通して国民の心の健康と全国の地域における経済活動の発展に寄与することを目的としています。
団体設立年月日
2023年11月29日
ニーズ・背景
核家族化が進み、子育て中のママさんやパパさんの負担、またコロナ禍でソーシャルディスタンスを余儀なくされ昔はあったはずの当たり前の「世代を超えた交流」がなかなか出来なくなりました。家族以外の世代を超えた人と交流を深める事は必ず良い化学反応が起こると確信しています。
母が90歳になりますが、なかなか人と関わる場所がありません。高齢者と未就学児が一緒に手遊びができたら楽しいと思います。また赤ちゃんにとっても家族以外の人と関わる事は良い事だと思います。
動機
未就学児対象にリトミックのような音楽遊びを毎月開催していますが、母が見学を非常に楽しみにしています。なかなかこのご時世、誰かわからない方との交流はしにくいのですが、だからこそ安心して来ていただけるような企画にしたいなと思います。
実施内容
未就学児と保護者、そして高齢者
期間は秋と春の2回
アオーレ長岡交流ホールAピアノ使用
NPO法人ミュージックライフパートナー理事達
期待する効果
世代を超えた交流はやるべきだと思います。
一日喋る事もない高齢者もいます。家族としか話さない人もいます。自分が高齢者になったとき赤ちゃんと一緒に遊べたらそれだけで幸せホルモンが出そうです。また赤ちゃんにとっても家族ではない人と交流すれば必ず良い反応が生まれます。また声楽家の歌声で手遊びができるのはなかなかないチャンスだと思います。
実現に向けて足りないもの
資金が助かります。あと、宣伝をしてくださる方、フォロワーが多いインフルエンサーがご協力いただけると嬉しいです。
長岡とパワエレの絵本の制作・頒布
安達 裕さん
ニーズ・背景
パワーエレクトロニクス(パワエレ)とは、効率よく電気を変換したり制御する技術のことで,電気を使うあらゆる機器に使われています。
二酸化炭素の排出削減にもつながる事から,近年注目が集まっている技術です。
長岡は世界でも類稀なパワエレ技術の集積地であり,2022年には長岡技大,パワエレ関連企業,長岡市の三者が産学官連携組織「長岡パワーエレクトロニクス研究会」を設立し,さらなる技術の向上,雇用創出を目指し「パワエレのまち長岡」を掲げて活発に活動しています。
しかしパワエレ自体が一般的に知られていない技術である為,この動きは業界内に留まっているのが現状です。
そこで私は業界外の方々に広くパワエレを知ってもらうきっかけが必要であると考えています。
動機
私自身が文系出身で,もともと技術にあまり興味は無く,パワエレの事も知りませんでしたが,数年前に前職で仕事をする中で“長岡はパワエレのメッカであること”を知り,自分のまちの自慢話をひとつ手に入れた気持ちになりました。
そして今,世界的にパワエレへの注目が高まり,パワエレについての話は長岡人が知る価値がある情報だと思い,伝えたいと思ったからです。
実施内容
- 長岡の未来を担うこどもたちに向けて長岡とパワエレを題材とした絵本を制作,頒布
- こどもたちとその親世代へ,パワエレを知ってもらう,興味を持ってもらうきっかけを作る
- 絵本の内容案(概要):舞台は長岡,パワエレ博士が隠し持っていたスーパーパワーデバイスを化けタヌキが食べ物と間違えて食べてしまった事で,電気を自在に操る力を手に入れ,LEDを光らせたり,乗り物を動かしたりして大活躍するお話
- 期間:2025年内発行し,それ以降に何等かのイベントか書店での配布,または販売
- 場所:未定
- 協力者:長岡パワーエレクトロニクス研究会,長岡パワーエレクトロニクス株式会社,長岡技術科学大学パワーエレクトロニクス研究室,FMながおか,長岡造形大学 渡辺誠介先生
- 特にアピールしたいポイント:
広く一般の方々にパワエレを知ってもらうには,“絵本として面白い物を作ること”がこのプロジェクトで最も重要であると考えています。
“パワエレを絵本にしたから面白い物”では,業界内か既にパワエレに興味を持っている方にしか届かない可能性が大きいが,絵本としての面白さを充分に備えている物であれば,一番の狙いとしている業界外の方に届く可能性が生まれると思うからです。
期待する効果
“パワエレのまち長岡”が長岡市民にとっての新しい誇りになって,結果20年後には道の駅ながおかパワエレ館が出来ます。
もしくは長岡テクノポリス構想の火が再び大きく燃え上がり,幻のテーマパークスペースネオトピアがパワエレネオトピアとして開園します。
上記の半分は冗談ですが,地域の誇りになる → 技術・産業分野の枠を飛び越えて観光資源にもなりえると私は思っており,誰にとっても無関係な話では無いと考えています。
実現に向けて足りないもの
絵本制作に協力してくれる人(話を一緒に考えてくれる人,絵を描いてくれる人),発表の場,頒布(配布または販売)の場
青柳 拓さん
団体名
越後川口エンジン
団体の目的または設立の背景
できる範囲でやる地域の賑わい創出
ニーズ・背景
当団体「越後川口エンジン」は、拠点である『まちの暮らしラボ』(以下、『ラボ』)の活用をしている。空き家であるこの場所は、イベントスペースとして定期的に使用してきたが、より活用の機会を増やしたいと思っていた。
一方で、近所の人たちからはお茶を飲んで話すスペースが欲しい、との声が多数あった。
動機
カフェが好きな人は多くいるが、自分のカフェをやってみたいという人も一定数いることが分かった。ところが、カフェは初期投資や売上の面でなかなか実行に移せない人が多い。
一方で、近所の人たちは憩いの場としてカフェを求めていた。
この2つを両立させるために思いついたのが、自分のカフェを持ちたい人向けに『ラボ』を貸しだすことである。
実施内容
- カフェを気軽に始めたい人のための『1日カフェ』
- カフェの道具が揃えられない人のための『カフェ道具一式のレンタル』
- 利用料¥2000、カフェ道具レンタル一式¥2000、のような『シンプルな料金体系』
期待する効果
- 地域→近所のにぎわい創出、空き家対策
- 出店者→低コストでカフェの経営感覚を身に付けられる、カフェの収入
実現に向けて足りないもの
広報活動
雪国でコーヒー栽培したい
本間 知美さん
ニーズ・背景
昨今の世界情勢の悪化や自然環境の変化に伴い100%に近い輸入のコーヒーは、年々値上がりしており更なる値上がりがこの先も懸念される。
コーヒーは嗜好品でありながらも多くの人の日常に深く入り込み、ホッとするための時間や人と人を繋ぐ大切な飲み物だと認識しているものでもある。
輸入もしつつ、日本産のコーヒーも作れたらこの先も安定供給できるのではないかと考えた。
何より南国でしか作れないコーヒーのイメージを雪国で栽培できたらかなりな話題となり、長岡や新潟県のアピールになるとおもう。
動機
夫がコーヒー焙煎士であり、現在コーヒー豆のネットショップをしています。
農作物としてのコーヒーに興味を持ちました。
実施内容
コーヒーを日本で栽培しているところはすでにありますが、栽培条件として、新潟県の場合はハウス栽培でないと難しい。
岡山県でハウス栽培に成功したやまこうファームという企業があり、
そこが栽培のノウハウをもっている。
ハウスと土地、燃料代があれば、ノウハウを教えることは可能と言われた。育てて販売して売れなかったらやまこうで買い取ってくれるシステムのようだ。
(金額や詳細はまだ聞いていません)
期待する効果
移住相談員として地域の活性化やまちの魅力アピールにも繋がれば面白いなと感じました。
実現に向けて足りないもの
ズバリ資材や管理ノウハウを習う資金。
一緒に育ててくれる協力者。
ハウス栽培をしていて離農する方から譲り受けたり、すでに熱帯植物を育てているところに一緒に植えたりできないか?などは検討できるかもしれない。
最低でも苗から収穫まで3年ほどかかるのでは?
マネタイズできるまでの収入源。